こんにちは!
さきです🌼
今回は
「過去問」
についてです!
教員採用試験の
勉強を進める中で
「過去問は
何年分解けばいいの?」
という
疑問をもつ方は
多いのでは
ないでしょうか。

過去問を活用するときの
最適な年数
効果的な勉強法
そして注意点について
詳しく解説します!
過去問は何年分解くべきか?
過去問は
3〜5年分
を目安に解くのが
効果的です!
理由は以下の通りです。
1. 出題傾向を把握できる
試験の
内容や形式は
大きく
変わらないことが
多いため
数年分解けば
「よく出るテーマ」
が見えてきます。

2. 自分の弱点を発見できる
過去問を
解くことで
苦手分野を明確にし
重点的に対策が◎
3. 試験の時間配分に慣れる
実際の
試験時間を
意識しながら
解くことで
本番での
ペース配分の
練習になります!
可能なら
10年分に
挑戦するのもアリ(?)
専門科目は
過去10年の間に
繰り返し
出題される問題が
あるらしいので
長期間の傾向を
分析することで
より確実な対策が
できる可能性も。

ただ
さかのぼっていくと
傾向が変わっている
年がある
と思うので
そのくらいまで
できれば
いいかなと
思います!
過去問の効果的な活用方法
① まずは1年分を
解いて実力チェック
最初に1年分
(直近のもの)を
時間を計って
解いてみましょう。
これにより
自分の
現在の実力や
苦手分野が
明確に
なります!
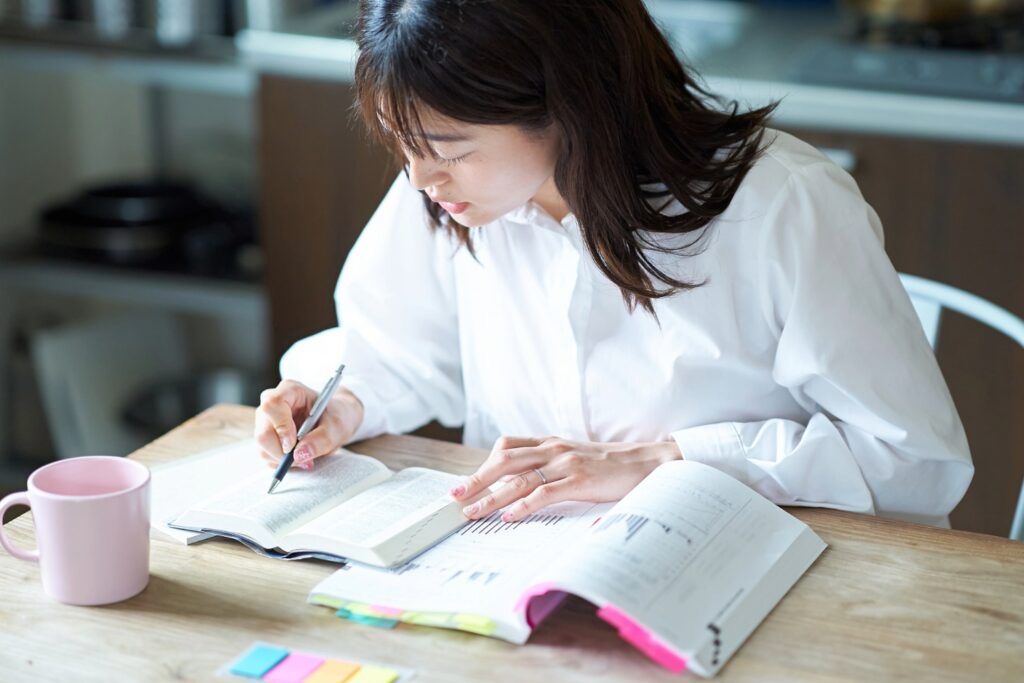
② 解説を読み込みながら
復習する
解いた後は
必ず解説を
じっくり読み込みましょう。
間違えた問題は
なぜ間違えたのかを
分析し
知識を補強することが
大切です。
③ 分野ごとに
過去問を整理する
1年分ずつ
解くだけでなく
教科ごと・単元ごとに
問題を分類して
解くのも
効果的です。
例えば
数学なら
「数と計算」
「図形」
「関数」などに
分け
弱点補強に
活用できます。

④ 2周目・3周目で
定着させる
1回解いただけでは
知識が定着しません。
最低でも
2〜3回は
繰り返し
解きましょう。
特に間違えた問題は
ノートにまとめ
すぐに
見返せるようにすると
良いです♩
⑤ 模試や予想問題と
組み合わせる
過去問だけでなく
模試や予想問題も
活用しましょう。
本番では
新傾向の問題が
出ることもあるため
さまざまなパターンの
問題に
慣れておくことが
重要です!

過去問を解く際の注意点
① 解答を暗記しない
「答えを覚えてしまった」
という状態では
意味がありません。
解くときは
「なぜその答えになるのか」
を理解すること
を意識しましょう。
② 最新の試験制度を
確認する
試験の形式や
出題範囲が
変更されることが
あります。
最新の試験要項を
必ずチェックし
古すぎる過去問は
出題傾向が異なる可能性が
あることに
注意しましょう⚠️

③ 過去問だけに頼らない
過去問は
重要な教材ですが
それだけでは
不十分です。
基礎知識が
抜けていると
応用問題に
対応できません。
教科書や参考書を
使って
基礎固めも
しっかり行いましょう。
④ できなかった問題を
放置しない
「解けなかった問題」を
そのままにしないことが
大切です!
わからなかった問題は
・参考書で調べる
・解説を読む
・ノートにまとめる
などの工夫をして
確実に
理解しましょう。
まとめ
いかがでしたか?

過去問を
上手に活用すれば
教員採用試験の
合格率はぐっと
上がります!
計画的に
勉強を進めて
自信をもって
本番に
挑みましょう!
さき🌼
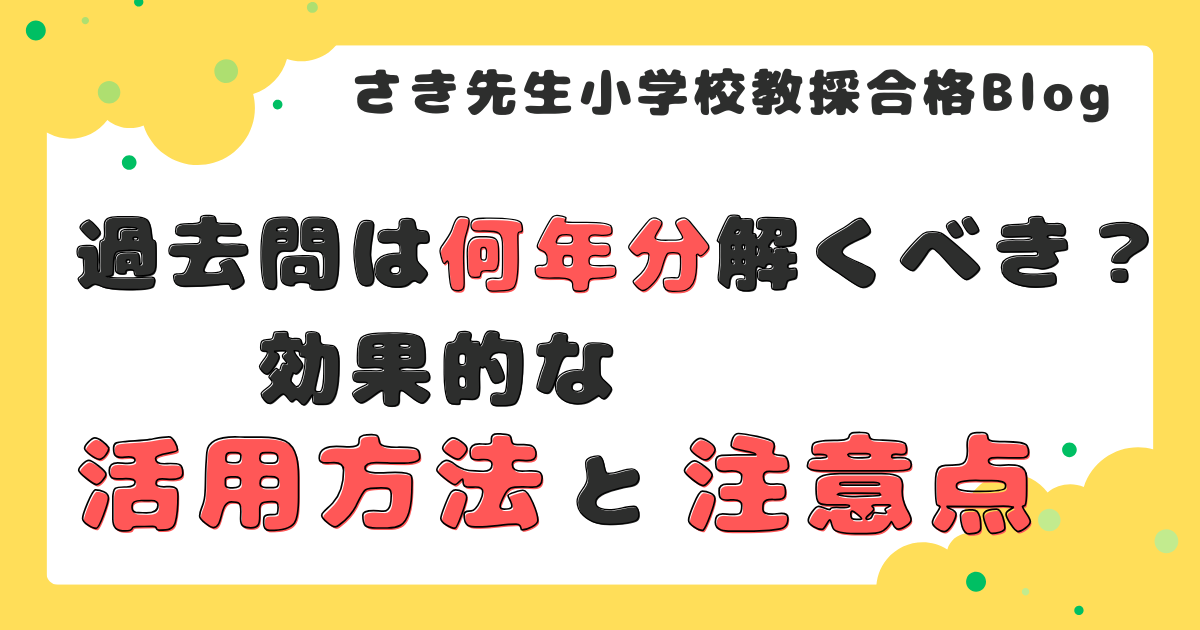


コメント